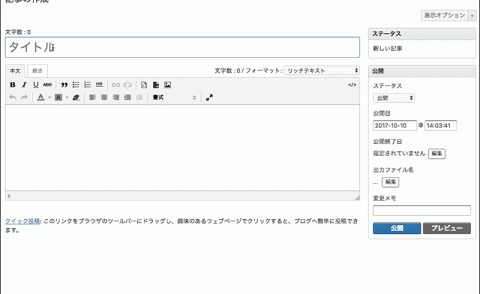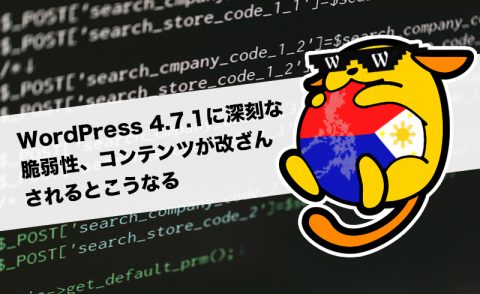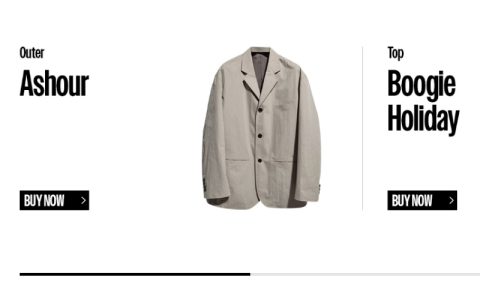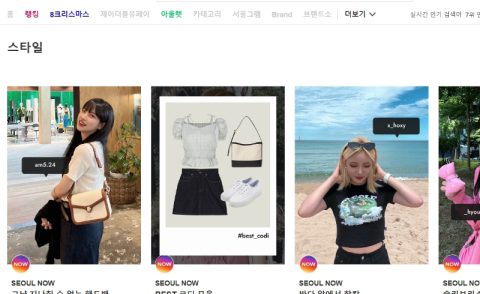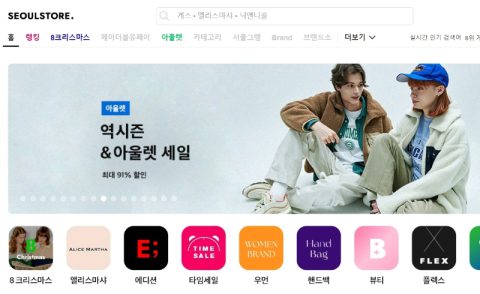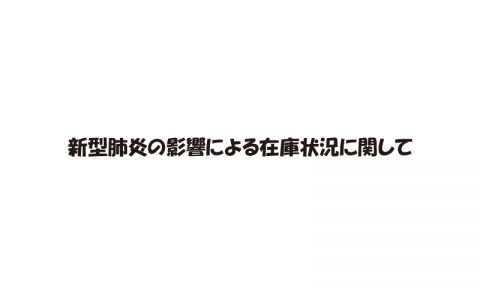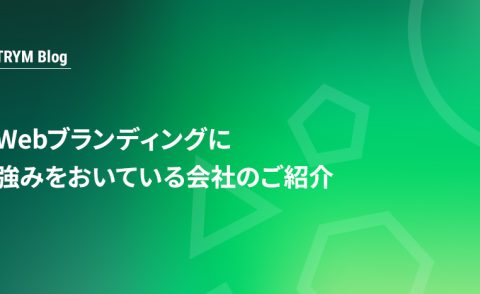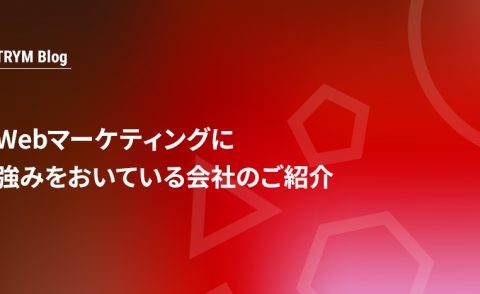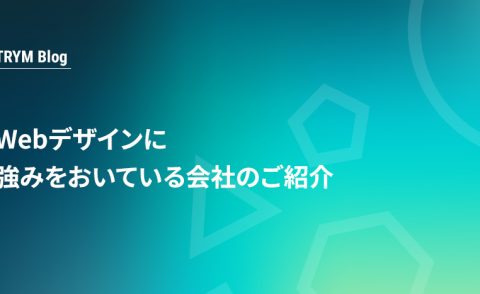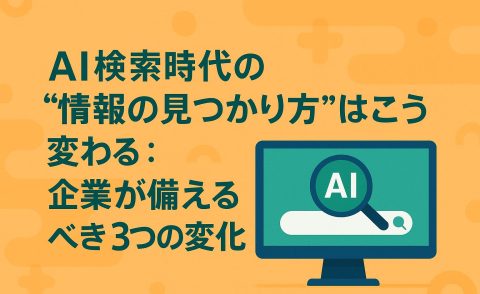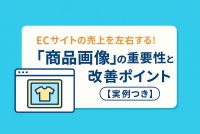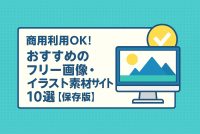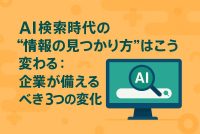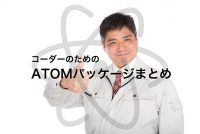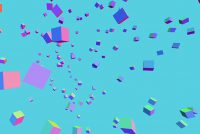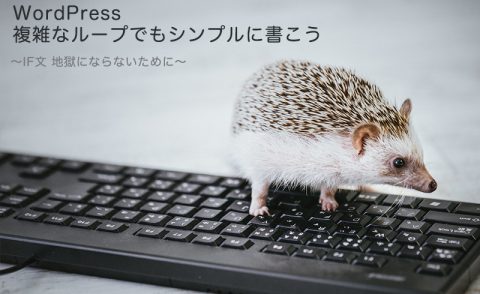
ホームページに“載せすぎ”はNG?情報設計の基本ルール
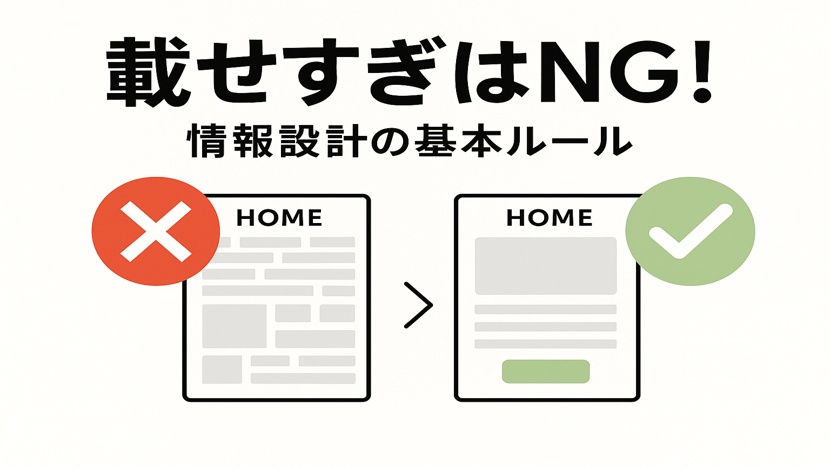
「せっかくホームページを作ったのに、見てもらえていない」
「伝えたいことは全部書いたのに、反応がない…」
そんなとき、原因は“情報の載せすぎ”かもしれません。
実は、Webサイトは**「情報量が多ければ良い」わけではなく、伝え方・見せ方が非常に重要**です。
この記事では、ユーザーに正しく伝えるための情報設計(インフォメーションアーキテクチャ)の基本ルールを紹介します。
「全部載せたい」が逆効果になる理由
Webサイトはパンフレットとは違い、ユーザーが自分で操作して見るという特性があります。
情報が多すぎると、次のようなことが起きがちです。
- どこを見ればいいか分からず、離脱される
- 重要な情報が埋もれてしまう
- 「結局この会社は何をしてるの?」という印象になる
つまり、「伝えたいこと」よりも「伝わること」を優先すべきなのです。
情報設計の基本ステップ
1. ユーザーの目的を明確にする
「誰が」「何のために」サイトを見るのかをまず整理しましょう。
例:商品購入/会社情報の確認/採用情報を探している など
2. 情報をグループ分けする
似た内容を1つのまとまりにし、ページ単位で構成を考えます。
例:
- サービス紹介 → 目的・特長・料金
- 会社情報 → 代表挨拶・アクセス・沿革
3. 優先順位をつける
「すべて重要」ではなく、ユーザーにとっての重要度で並べ替えます。
上から順に見られることを意識して設計します。
「1ページ1メッセージ」が基本ルール
1ページに複数の話題が混ざっていると、ユーザーは混乱します。
そのため、1ページにつき伝える内容は1テーマに絞るのが基本です。
例:
× 「サービス説明と会社紹介を1ページにまとめる」
○ 「サービスはサービスページ」「会社情報は会社情報ページ」に分ける
分けることで、検索エンジンからの評価も高まりやすくなります。
「視線の流れ」と「導線」を意識する
ユーザーの視線は左上→右下に動く傾向があります。
それに沿って以下のような配置を心がけましょう。
- 最も伝えたいことはファーストビュー(最上部)に
- ボタンやリンクはわかりやすく配置
- 誘導先のページには「続きを知りたい人向け」の情報を置く
サイト内での“迷子”を防ぐためにも、ナビゲーションの明確さは重要です。
「載せない」こともユーザーへのやさしさ
情報設計で大切なのは、「何を載せるか」と同じくらい「何を載せないか」です。
ユーザーの集中力や時間は限られているため、不要な情報は思い切って省くことも戦略の1つです。
伝わるWebサイトを一緒に考えてみませんか?
何を載せるべきか自信がない」
「情報を整理したいけど、自分たちでは難しい…」
そんな方のために、当社では情報設計に関する相談を承っております。
ヒアリングを通じて、伝わる構成・導線の設計をご提案いたします。
是非お気軽にお問い合わせください。
Writer
nemo
会社でアニ研(アニメ研究会)を設立したりするヲタク系Webディレクターです。
大切なことは音楽とアニメと漫画から教わりました。